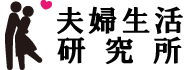| 破綻主義 (はたんしゅぎ) |
夫婦間の共同生活関係が客観的に破綻し、和合回復の見込みがなくなった場合にそれについての当事者の責任の有無を問わず離婚を認める立法上の立場のこと。いままでは有責主義という考え方が主流でしたので、相手に不貞行為があった場合にのみ離婚が認められていました。昭和62年から、一定の条件のもと有責配偶者からの離婚請求が認められるようになりました。一定の条件とは
となっています。 |
| 非嫡出子 (ひちゃくしゅつし) |
法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。 |
| 夫婦間契約の取り消し (ふうふかんけいやくのとりけし) |
民法第754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。他人ではない夫婦間の事については、法律は一歩引いて「法は家庭に入らず」というスタンスを示しているものといえます。但し、婚姻関係が実質的に破綻している場合は、形式的には婚姻中であっても、夫婦間の契約取消は許されません。 |
| 夫婦別産制 (ふうふべっさんせい) |
夫婦のどちらかが結婚する前からすでに持っていたり、結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の特有財産であるということです(民法762条1項)。つまり法律上結婚によって財産関係が特別に扱われることにはならず、原則として「自分の物は自分の物」であるということです。 |
| 不受理申出制度 (ふじゅりもうしでせいど) |
離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要です。夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。書式さえ整っていれば受理されてしまいます。そこで、本人が知らないところで離婚が成立してしまうことを防ぐために、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。 |
| 不貞行為 (ふていこうい) |
いわゆる浮気です。一般的な浮気と異なるのは、あくまで肉体関係の有無で判断されるということです。従って、食事をしたりキスをするといった事では不貞行為とは認められません。 |
| 扶養義務 (ふようぎむ) |
扶養義務には「民法上の扶養義務」と「社会保険上の扶養義務」の二つがあります。
|
| 扶養的財産分与 (ふようてきざいさんぶんよ) |
離婚によって、夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与のこと。離婚しても夫婦共に収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合や、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。 |
この記事を書いた人
- 1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。